赤ちゃんや幼児がティッシュを次々と引っ張り出して遊ぶのは、多くの親が経験することですよね。
「またやってる!」とイライラすることもあるかもしれませんが、実は、子どもの発達にとって大切な行動なんです!
今回は、その行動をなぜやるのかと科学的な原理について解説します。
なぜ子どもはティッシュをばら撒くのか?
指先の発達を促すため(運動発達)
生後6〜10ヶ月頃になると、手の動きがどんどん器用になります。
ティッシュをつまんで引っ張る動作は「指先のトレーニング」になっています。
特にこの時期の赤ちゃんは、
「親指と人差し指でつまむ」動きを習得中(ピンセット動作)
手の力加減を学んでいる(強く引くとちぎれる、そっと引くと長く出てくる)
「ティッシュを引っ張る→形が変わる→面白い!」という体験を繰り返して学習しているんです。
因果関係を学んでいる(認知発達)
赤ちゃんは「自分の動作がどんな結果を生むのか」を試すのが大好きです。
ティッシュの箱を発見したら、
ちょっと引っ張ると次のティッシュが出てくる!
もっと引っ張るとどんどん出てくる!
この「引っ張る→出てくる」の因果関係を理解しながら、試行錯誤しているんです。
物の特性を探求する(感覚遊び)
赤ちゃんにとって、ティッシュはただの紙ではなく、
薄くてヒラヒラする
軽くて舞い上がる
やぶれる!びりびり楽しい
という、さまざまな触覚・視覚の刺激を与えてくれる魅力的な存在です。
この行動を見た時は「これはどんなもの?」と探索しているんだなと思ってあげましょう
ママ・パパの反応が楽しい!
ティッシュをばら撒くと、大人が「ダメー!」と慌てることが多いですよね。
私たちも思わずやってしまいます。
子どもはそれを見て、「あれ?これやると面白い反応が返ってくる!」と学習します。
ママが笑ったのを見て、もっとやろう
パパが驚いたのを見て、これすごいことなのかも
このようにして「ティッシュ遊び=楽しい」と記憶に刻まれてしまうことがあります。
ティッシュ遊びの科学的な背景
ティッシュ遊びは、「モンテッソーリ教育」や「ピアジェの認知発達理論」にも通じる発達のステップです。
モンテッソーリ教育的観点
モンテッソーリ教育では、「子どもは自ら学ぶ力を持っている」と考えられています。
ティッシュを引っ張る行動は、手指の器用さを育てる「敏感期」の一環と捉えられます。
モンテッソーリでは、ティッシュの代わりに「布を引っ張り出すおもちゃ」などを使い、発達を促す環境を整えます。
ピアジェの認知発達理論(感覚運動期)
スイスの心理学者ピアジェは、乳児期(0〜2歳)を「感覚運動期」と呼んでいます。
この時期の子どもは、
触る
動かす
試す
といった動作を通じて、「物の性質」や「自分と世界の関係」を学びます。
ティッシュをばら撒く行動も、この発達の一環なのです。
オペラント条件付け(学習心理学)
「行動 → 結果 → その行動が強化される」
これが学習心理学の基本原理です。
ティッシュを引っ張るとどんどん出てくる!(楽しい!)
ティッシュをばら撒く とママが笑う or 驚く(リアクションが面白い!)
これを繰り返すことで、ティッシュ遊びが強化されることもあります。
どう対応するのが正解?
赤ちゃんがティッシュで遊ぶのは、成長の証。
でも、ティッシュがもったいないし、片付けも大変。
そんなときは、以下の対策を試してみましょう!
ティッシュを手の届かない場所に移動(物理的に防ぐのが一番!)
代わりに「引っ張る遊びができるおもちゃ」を用意する(モンテッソーリ式)
リアクションしすぎない(「面白い!」と学習させない)
「ティッシュは拭くもの」と教える(成長に合わせてルールを伝える)
ティッシュ遊びを「ダメ!」と一方的に止めるのではなく、発達の視点を理解しながら、うまく対策していくことが大切です。初めは思わず言ってしまいがちですが、親が少しずつ慣れていき、子供がのびのびと成長できる環境にしていきましょう
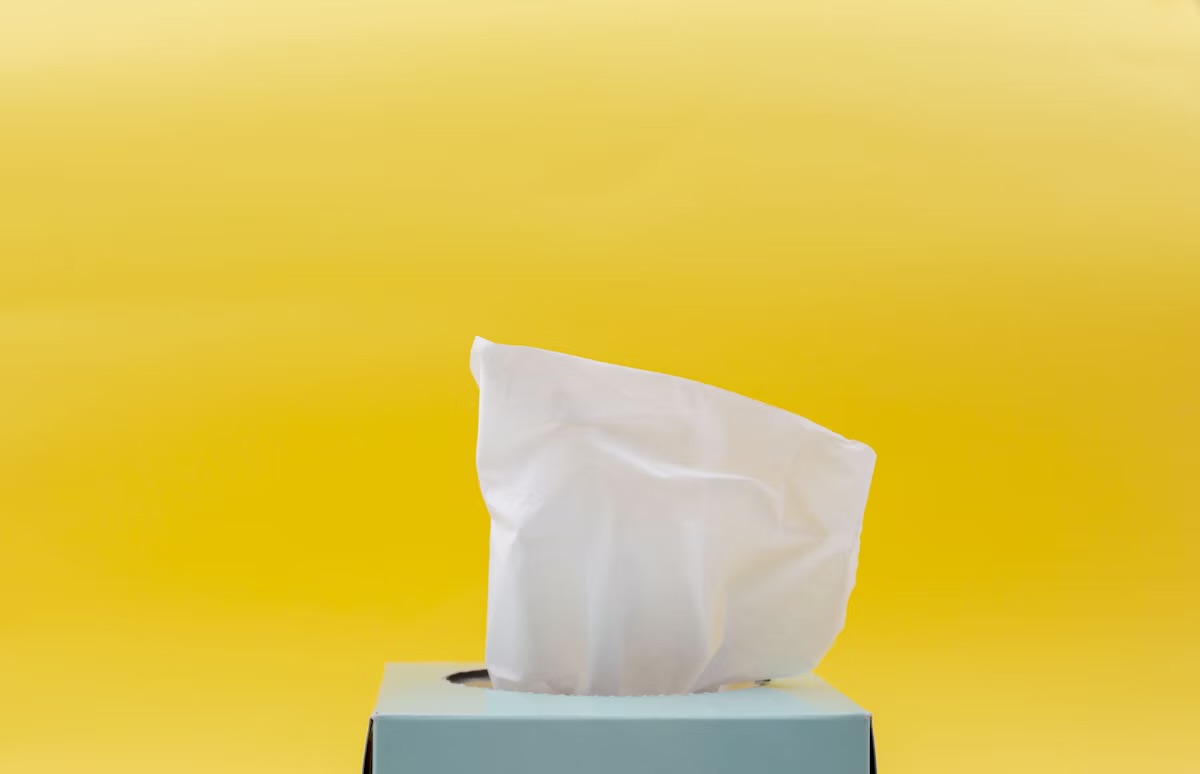


コメント